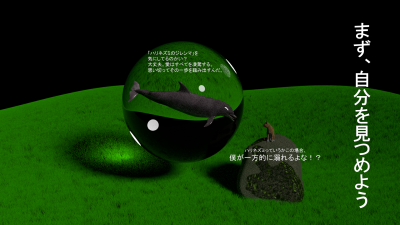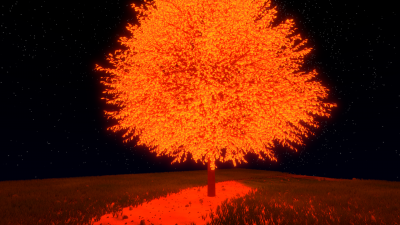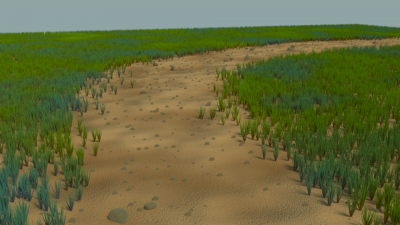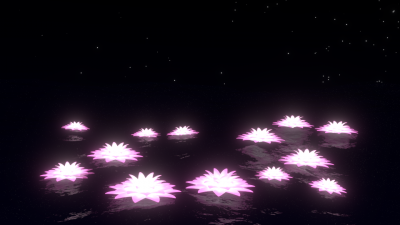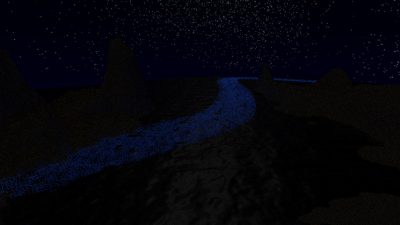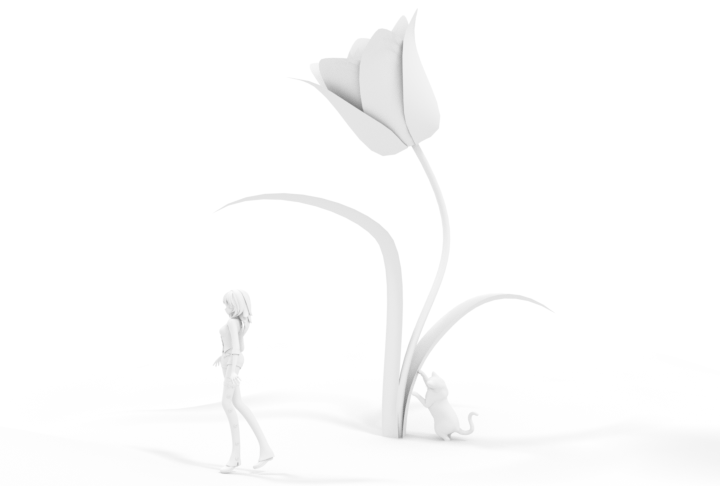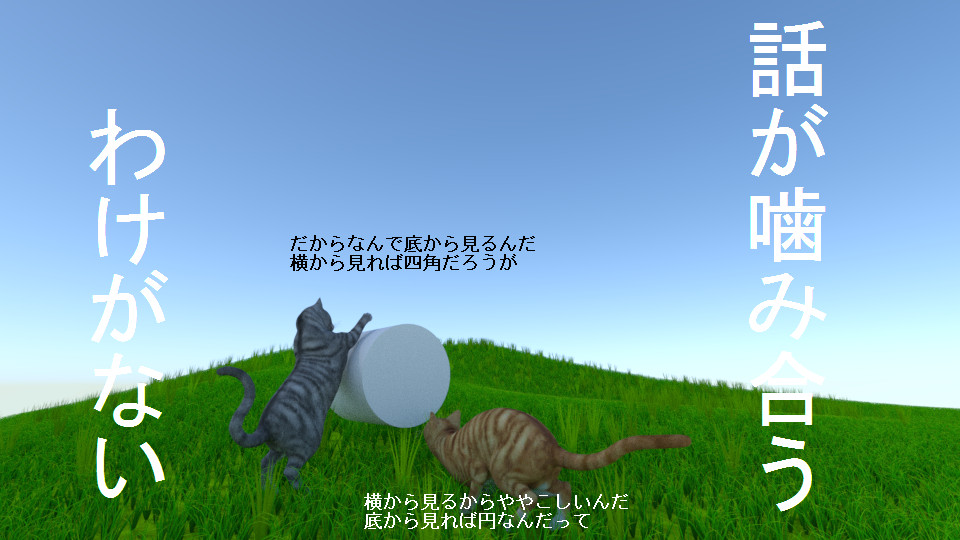月火水木金土日
2017/06/09 18:50 夕日
まず、自分を見つめよう
人は自分の信念を持っている。
それが自分にとってどんなに正義でも、過信してはいけない。
相手には相手の性格があり、癖があり、人生がある。
誰にでも分け隔てなく正しい答えなど、本当にあるのだろうか・・・
Blender/Cycles 練習 作品No.00011 燃えるような木
Blender/Cycles 練習 作品No.00010 道
Blender/Cycles 練習 作品No.00009 夜の花
Blender/Cycles 練習 作品No.00008 夜+海
スカイドーム
http://blender.stackexchange.com/questions/13853/create-hdr-map-from-render
をレンダリング。夜空のスカイドームを作って、海はOceanモディファイア。
ウミホタルの画像を検索してそれっぽく光らせる。