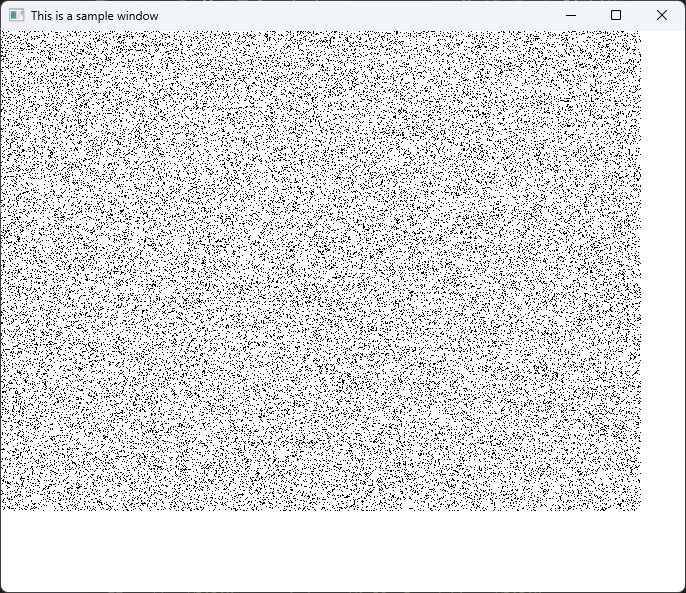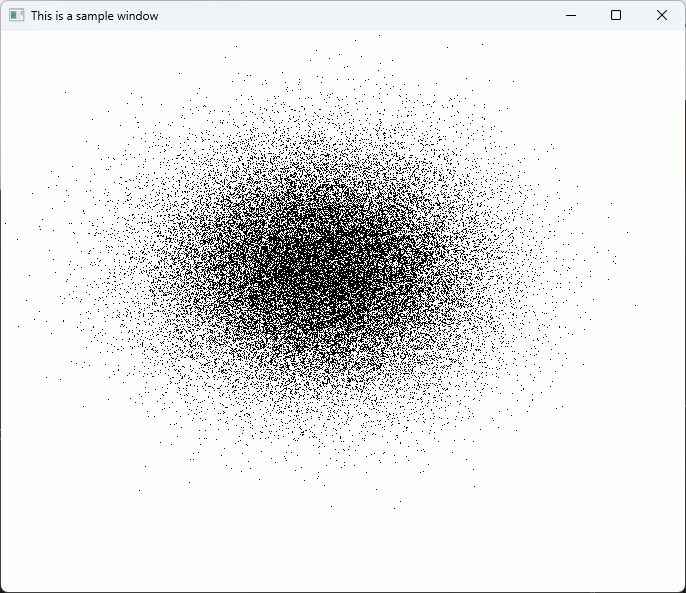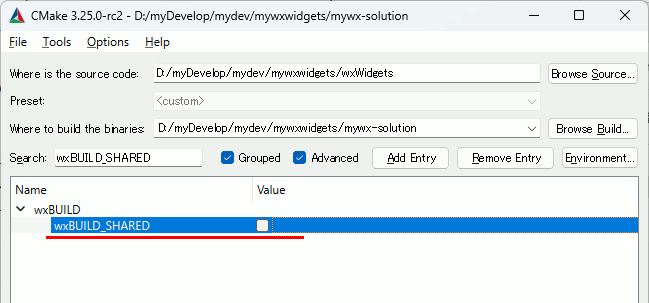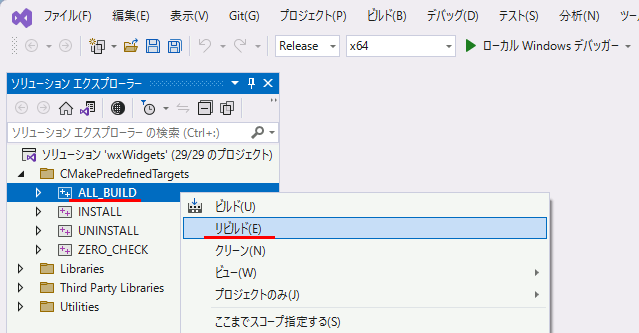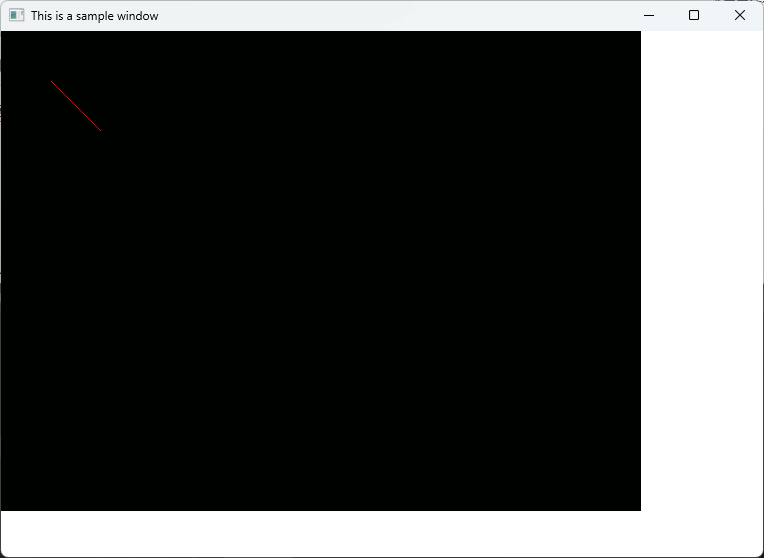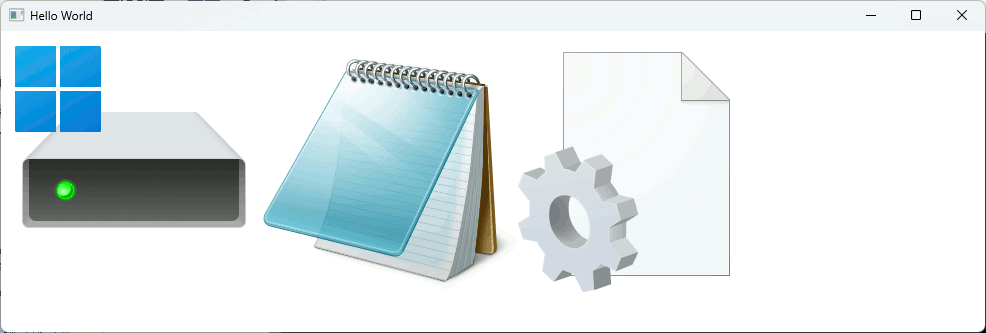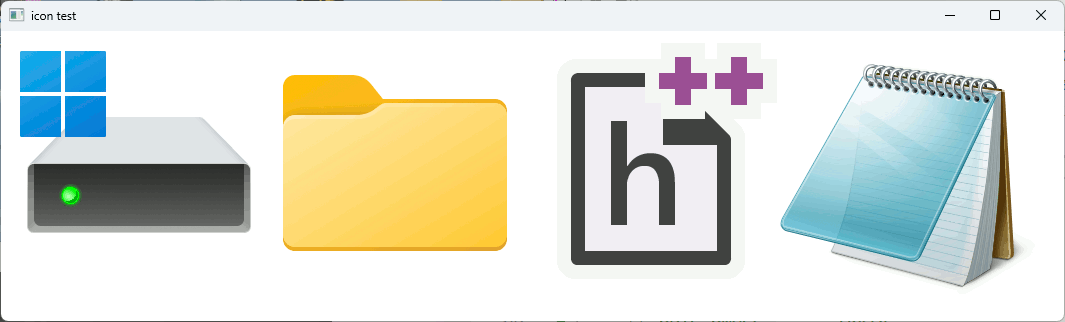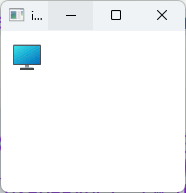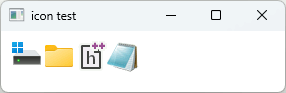Rustで乱数
Rustの乱数の使い方。
サンプルコード
Cargo.toml
乱数を使用するためにはrandクレートを使用する。
# 乱数を使用 https://crates.io/crates/rand
rand = "0.8.5"
最も基本的なコード
fn main() { use rand::Rng; // 乱数を使うためにrand::Rngを使用 let mut rng = rand::thread_rng(); let min:i32 = 0; let max:i32 = 20; // 50回ループ (0..50).for_each(|_|{ let randint:i32 = rng.gen_range(min..max); // 最大・最小を指定して乱数を生成 println!("{}",randint); }); }
分布を指定して乱数生成
rand_distrクレートを使用すると分布を変えられる。rand_distr::Normalは正規分布。
[dependencies]
# 乱数を使用 https://crates.io/crates/rand
rand = "0.8.5"
# 乱数の分布を指定 https://crates.io/crates/rand_distr
rand_distr = "0.4.3"
fn main() { use rand::prelude::{Distribution, thread_rng}; use rand_distr::Normal; let mut rng = rand::thread_rng(); let mean:f32 = 10.0; let stddev:f32 = 8.0; // 平均値と標準偏差を用いた乱数生成器を作成 let normal = Normal::new( mean, // 平均 stddev // 標準偏差 ).unwrap(); // 50回ループ (0..100).for_each(|_|{ let randint:i32 = normal.sample(&mut rng) as i32; // 乱数を生成 println!("{}",randint); }); }
win32apiで二次元にランダムな点をプロット
これだけではさすがにつまらないので、win32apiを使ってSetPixelで点を散布してみる。
以前作ったメモリデバイスコンテキストのコードで乱数のプロットを表示する。
winmain.rs
#[path="./win32dib.rs"] mod win32dib; use win32dib::Win32DIBCanvas; use windows::{ core::*, Win32::Foundation::*, Win32::Graphics::Gdi::*, Win32::UI::WindowsAndMessaging::*, }; use once_cell::sync::Lazy; use std::sync::Mutex; // ■ Mutex ... std::sync::Mutex // ■ Lazy ... once_cell::sync::Lazy static mydib:Lazy<Mutex<Win32DIBCanvas>> = Lazy::new(|| Mutex::new( Win32DIBCanvas::new() ) ); /////////////////////////////////////////////// /// MemDCの背景をクリア ////////////////////// fn clear_mydib_background(rmdib : &mut Win32DIBCanvas){ // super::super::Foundation::COLORREF // let refmydib = &mut mydib.lock().unwrap(); let width:i32 = rmdib.bitmapInfo.bmiHeader.biWidth; let height:i32 = -rmdib.bitmapInfo.bmiHeader.biHeight; let rect:RECT = RECT{ left:0, top:0, right:width, bottom:height, }; unsafe { let whitebrush = CreateSolidBrush(COLORREF(0x00FFFFFF)); FillRect(rmdib.hMemDC,&rect,whitebrush); DeleteObject(whitebrush); } }
/////////////////////////////////////////////// /// count個の乱数を生成 fn get_random(count:i32, min:i32,max:i32) -> Vec<i32>{ use rand::Rng; // 乱数を使うためにrand::Rngを使用 let mut rng = rand::thread_rng(); let mut rlist:Vec<i32> = Vec::new(); for i in 0..count{ let randint:i32 = rng.gen_range(min..max); rlist.push(randint); } return rlist; }
/////////////////////////////////////////////// // ■ HWND ... windows::Win32::Foundation::HWND // ■ WPARAM ... windows::Win32::Foundation::WPARAM // ■ LPARAM ... windows::Win32::Foundation::LPARAM // ■ LRESULT ... windows::Win32::Foundation::LRESULT extern "system" fn wndproc(window: HWND, message: u32, wparam: WPARAM, lparam: LPARAM) -> LRESULT { unsafe { // ■ RECT ... windows::Win32::Foundation::RECT let rectnullptr: Option<*const RECT> = None; match message as u32 { WM_CREATE => { // mydib.lock().unwrap() への可変な参照をrefmydibに束縛 let refmydib = &mut mydib.lock().unwrap(); refmydib.create(640,480); clear_mydib_background(refmydib);
/////////////////////////////////////// /// 乱数で座標を作成 ////////////////// let count = 50000; let xlist:Vec<i32> = get_random(count,0,640); let ylist:Vec<i32> = get_random(count,0,480); // 点をプロット for pindex in 0..count as usize{ SetPixel( refmydib.hMemDC, xlist[pindex], ylist[pindex], COLORREF(0x00000000)); } ///////////////////////////////////////
// ■ LRESULT ... windows::Win32::Foundation::LRESULT LRESULT(0) } WM_PAINT => { // ■ PAINTSTRUCT ... windows::Win32::Graphics::Gdi::PAINTSTRUCT // ■ BeginPaint ... windows::Win32::Graphics::Gdi::BeginPaint let mut ps = PAINTSTRUCT::default(); let hdc = BeginPaint(window, &mut ps); let refmydib = &mut mydib.lock().unwrap(); ////////////////////////////////////////////////////////// // 背景をクリア /////////////////////////////////////////// let mut clientrect:RECT = RECT::default(); GetClientRect(window, &mut clientrect); let whitebrush = CreateSolidBrush(COLORREF(0x00FFFFFF)); FillRect(hdc,&clientrect,whitebrush); DeleteObject(whitebrush); ////////////////////////////////////////////////////////// // ■ BitBlt ... windows::Win32::Graphics::Gdi // ■ SRCCOPY ... windows::Win32::Graphics::Gdi::SRCCOPY BitBlt( hdc, 0, 0, 640, 480, refmydib.hMemDC, 0, 0, SRCCOPY ); // ■ EndPaint ... windows::Win32::Graphics::Gdi::EndPaint EndPaint(window, &ps); // ■ LRESULT ... windows::Win32::Foundation::LRESULT LRESULT(0) } WM_DESTROY => { println!("WM_DESTROY"); // ■ windows::Win32::UI::WindowsAndMessaging::PostQuitMessage PostQuitMessage(0); // ■ LRESULT ... windows::Win32::Foundation::LRESULT LRESULT(0) } // ■ windows::Win32::UI::WindowsAndMessaging::DefWindowProcA _ => DefWindowProcA(window, message, wparam, lparam), } } } // ■ HINSTANCE ... windows::Win32::Foundation::HINSTANCE /// 自作 WinMain pub fn WinMain( hInstance : HINSTANCE, hPrevInstance : HINSTANCE, lpCmdLine:Vec<String>, nCmdShow:i32 )->i32{ unsafe{ // ■ PCSTR ... windows::core::PCSTR // ■ windows::Win32::UI::WindowsAndMessaging::LoadCursorW // ■ windows::Win32::UI::WindowsAndMessaging::IDC_ARROW // ■ windows::Win32::UI::WindowsAndMessaging::CS_HREDRAW // ■ windows::Win32::UI::WindowsAndMessaging::CS_VREDRAW let _hCursor = LoadCursorW(None,IDC_ARROW).unwrap(); let _hInstance = hInstance; let _lpszClassName = PCSTR::from_raw("MY_NEW_WINDOW\0".as_ptr()); let _style = CS_HREDRAW | CS_VREDRAW; // https://microsoft.github.io/windows-docs-rs/doc/windows/Win32/UI/WindowsAndMessaging/struct.WNDCLASSA.html // ■ WNDCLASSA ... windows::Win32::UI::WindowsAndMessaging::WNDCLASSA let wc=WNDCLASSA{ hCursor :_hCursor, hInstance: _hInstance, lpszClassName: _lpszClassName, style: _style, lpfnWndProc: Some(wndproc), ..Default::default() }; // ■ windows::Win32::UI::WindowsAndMessaging::RegisterClassA let atom = RegisterClassA(&wc); debug_assert!(atom != 0); let nullptr: Option<*const ::core::ffi::c_void> = None; // ■ windows::Win32::UI::WindowsAndMessaging::CreateWindowExA // ■ PCSTR ... windows::core::PCSTR // ■ windows::Win32::UI::WindowsAndMessaging::WS_OVERLAPPEDWINDOW // ■ windows::Win32::UI::WindowsAndMessaging::WS_VISIBLE // ■ windows::Win32::UI::WindowsAndMessaging::CW_USEDEFAULT CreateWindowExA( Default::default(), _lpszClassName, PCSTR::from_raw("This is a sample window\0".as_ptr()), WS_OVERLAPPEDWINDOW | WS_VISIBLE, CW_USEDEFAULT, CW_USEDEFAULT, 700, 600, None, None, _hInstance, nullptr, ); // ■ windows::Win32::UI::WindowsAndMessaging::MSG let mut message = MSG::default(); // ■ windows::Win32::UI::WindowsAndMessaging::GetMessageA // ■ windows::Win32::UI::WindowsAndMessaging::DispatchMessageA // ■ HWND ... windows::Win32::Foundation::HWND while GetMessageA(&mut message, HWND(0), 0, 0).into() { DispatchMessageA(&mut message); } } return 0; }
正規分布の乱数
先のプログラムのget_randomを以下のように変える(minは使わないことにした)と、乱数の分布が変わったのがわかる。
/////////////////////////////////////////////// /// 正規分布の乱数を生成する /////////////////// fn get_random(count:i32, max:i32) -> Vec<i32>{ use rand::prelude::{Distribution, thread_rng}; use rand_distr::Normal; let mut rng = rand::thread_rng(); // 平均値と標準偏差を用いた乱数生成器を作成 let normal = Normal::new( (max as f32) / 2.0, // 平均 (max as f32) / 8.0 // 標準偏差 ).unwrap(); let mut rlist:Vec<i32> = Vec::new(); for i in 0..count{ let randint:i32 = normal.sample(&mut rng) as i32;// 平均値と標準偏差で乱数生成 rlist.push(randint); } return rlist; }
シードを指定して乱数生成
シードを指定する場合、以下のように[u8;32]の配列をシードとして与える。シードだけで32byteも与えなければならない。なお[0;32]の配列指定で要素の型がu8に定まるのは、文脈的にseedがfrom_seedで与えられていることからデータ型を推論しているかららしい。
fn main() { use rand::Rng; // 乱数を使うためにrand::Rngを使用 use rand::SeedableRng; // シードの指定に必要 use rand::rngs::StdRng; // シードの指定に必要 let seed = [0; 32];// 全要素0、要素数32,u8型の配列を作成 let mut rng:StdRng = SeedableRng::from_seed(seed); // シードを固定した乱数生成器を初期化 //let mut rng = rand::thread_rng(); // シード未指定の場合 let min:i32 = 0; let max:i32 = 20; // 50回ループ (0..50).for_each(|_|{ let randint:i32 = rng.gen_range(min..max);// 最大・最小を指定して乱数を生成 println!("{}",randint); }); }
Blender 3.4とか4.0でGeometry NodeからDistribute Points on Faces
しばらく使っていなかったらGeometry nodeでオブジェクト周辺に点群を生成する機能の使い方が随分と変わっていたので更新しておきたい。初期のころはPoint Distributeとか呼ばれていたもののこと。
なお各ノードの追加はすべて[Shift+A]から検索している。
過去記事:
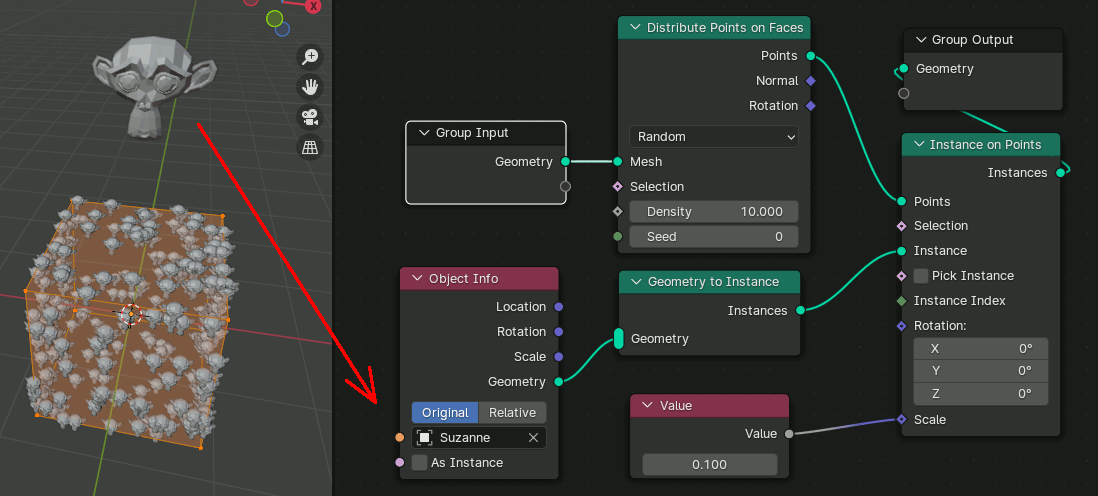
変数形式で入力しなければいけなかったところがノード接続になって好感が持てる。
検索して手間取ったのが生成するインスタンスを指定する方法が、Point InstanceからObject Info->Geometry to Instance とより抽象化されたところ。
C++のconceptについて超初歩的まとめ
(誤解を恐れずに言うなら)conceptはテンプレートで渡す際のclass TのTに条件を付けるための機能。
以下のように、
concept 条件名 = requires(T val){ ... }
という形で定義する。
型Tで与えられた変数valの使い方を定義すると考えると読みやすくなる。
#include <iostream>
// T型の変数valは、print()と++を持たなければならない
template <class T> concept CallableFunction = requires (T val) { val.print(); // print()関数があることを要求 val.operator++(); // ++演算子があることを要求 };
// CallableFunctionの制約がついている所で使用できるクラス class MyValidClass { int val; public: MyValidClass() { val = 5; } void print() {// print()関数を定義 std::cout << "val == " << val << std::endl; } MyValidClass& operator++() {// ++演算子を要求 ++val; return *this; } };
// CallableFunctionの制約がある場合は指定できない。 // operator++() がない。 class MyInvalid { int val; public: MyInvalid() { val = 5; } void print() { std::cout << "val == " << val << std::endl; } };
// print()関数と++演算子を持つクラスを引数に取る関数 template <CallableFunction Type> void func(Type val) { val.print(); }
int main() { MyValidClass my; func(my); }
式が有効でなければならないという要求を定義
{ } 内に式を書くと、その式を書くことができるような型だけを要求することができる。
#include <iostream> #include <algorithm> #include <vector>
template <class T> concept Sortable = requires (T& val) { // { } 内の式が有効であることを要求する書き方ができる。 // 例えば、以下は T 型の val はソート可能であることを要求する { std::sort(val.begin(), val.end()) }; };
// print()関数と++演算子を持つクラスを引数に取る関数 template <Sortable Type> void func(Type& val) { std::sort(val.begin(), val.end()); }
int main() { std::vector<int> my{ 5,3,8 }; func(my); for (auto& i : my) { std::cout << i << std::endl; } }
戻り値の要求
{ 式 } で、式が有効であることを要求できるが、式の結果のデータ型を要求するには
とする。
この仕組みを応用すれば、関数の戻り値を要求できる。
#include <iostream> #include <algorithm> #include <vector>
template <class T> concept Sizable = requires (T & val) { { val.size() // size()関数を持つ }->std::same_as<size_t>; // size()関数の戻り値はsize_t型 // std::same_asはconcept。式の戻り値の型を指定する。 };
class MyArray { std::vector<int>vec; public: void push_back(int i) { vec.push_back(i); } int size() { return vec.size(); } };
// この関数は、戻り値がsize_t型のsize()関数を持つ型しか受け付けない template <Sizable Type> void func(Type& val) { std::cout<<val.size()<<std::endl; }
int main() { std::vector<int> my; // MyArray my; my.push_back(3); my.push_back(1); my.push_back(8); func(my); }
wxWidgetsをstatic link libraryとしてビルドする
wxWidgetsを使用した場合の問題の一つが、配布時に同梱するDLLの数が増えることで、これを解決するためにwxWidgetsをStatic Link Libraryとしてビルドしてexeとくっつけてしまうことで、DLLの同梱を不要にする。
CMake
ダウンロード
まずソースコードをダウンロードするが、zipでは依存関係が多くて面倒なので、git clone --recursiveで依存関係も含め一括でダウンロードする。
cmake
CMakeでは、wxBUILD_SHAREDを検索し、このチェックを外す
ALL_BUILDをビルドし、INSTALLする。
使用方法
基本的な使い方はShared Libraryの時と同じだが、何点か注意点がある。
VC++でwxWidgetsを試す(1)
注意点
・WXUSINGDLL を指定しない
プリプロセッサにWXUSINGDLLを指定しない。指定してしまうとLNK2001が大量発生する
・windowsのlibファイルのリンクを追加
comctl32.lib , rpcrt4.lib をリンクする。
// プリプロセッサに以下を追加 // __WXMSW__ // static link library の場合、以下は指定しない // WXUSINGDLL // サブシステムをWindowsに設定(WinMainで呼び出すので) // Windows (/SUBSYSTEM:WINDOWS) #ifndef WX_PRECOMP #include <wx/wx.h> #endif #include <wx/gdicmn.h> // wxPointに必要 #include <wx/frame.h> // wxFrameに必要 // Win32 API #pragma comment(lib, "comctl32.lib") #pragma comment(lib, "rpcrt4.lib") // wxWidgets #pragma comment(lib,"wxmsw33u_core.lib") #pragma comment(lib,"wxbase33u.lib") #pragma comment(lib,"wxbase33u_net.lib") #pragma comment(lib,"wxbase33u_xml.lib") #pragma comment(lib,"wxexpat.lib") #pragma comment(lib,"wxjpeg.lib") #pragma comment(lib,"wxlexilla.lib") #pragma comment(lib,"wxmsw33u_adv.lib") #pragma comment(lib,"wxmsw33u_aui.lib") #pragma comment(lib,"wxmsw33u_gl.lib") #pragma comment(lib,"wxmsw33u_html.lib") #pragma comment(lib,"wxmsw33u_media.lib") #pragma comment(lib,"wxmsw33u_propgrid.lib") #pragma comment(lib,"wxmsw33u_qa.lib") #pragma comment(lib,"wxmsw33u_ribbon.lib") #pragma comment(lib,"wxmsw33u_richtext.lib") #pragma comment(lib,"wxmsw33u_stc.lib") #pragma comment(lib,"wxmsw33u_webview.lib") #pragma comment(lib,"wxmsw33u_xrc.lib") #pragma comment(lib,"wxpng.lib") #pragma comment(lib,"wxregexu.lib") #pragma comment(lib,"wxscintilla.lib") #pragma comment(lib,"wxtiff.lib") #pragma comment(lib,"wxzlib.lib") ///////////////////////////////////// ///////////////////////////////////// ///////////////////////////////////// // ウィンドウ作成 class MyFrame : public wxFrame { public: MyFrame(const wxString& title, const wxPoint& pos, const wxSize& size) : wxFrame(NULL, wxID_ANY, title, pos, size) { } private: // イベント処理しないときはこれを入れない // wxDECLARE_EVENT_TABLE(); }; ///////////////////////////////////// ///////////////////////////////////// ///////////////////////////////////// // wxWidgetsのアプリケーション作成 class MyApp : public wxApp { public: virtual bool OnInit() { MyFrame* frame = new MyFrame("Hello World", wxPoint(50, 50), wxSize(450, 340)); frame->Show(true); return true; } }; ///////////////////////////////////// ///////////////////////////////////// ///////////////////////////////////// // WinMainをマクロで定義 wxIMPLEMENT_APP(MyApp);
win32api タスクトレイアイコンをクリックしたときにメニューを表示
なんでもタスクトレイという言い方は正しくなく、通知領域、Notification Areaが正しいらしい。知ったことではない。
タスクトレイにアイコンを表示する方法を以前調べた。
タスクトレイにアイコンを表示する
クリックしたときにメニューを表示する場合、GetCursorPosでマウスカーソルの位置を取得して、TrackPopupMenuでメニューを表示する。
#pragma warning(disable:4996) #include <windows.h> #include <shellapi.h> static const int TasktrayIconID = 100; static const int WM_MY_NOTIFYICON = WM_USER + TasktrayIconID; const int ID_MENU_MSG = 100; const int ID_MENU_EXIT = 101; HMENU myCreateMenu(); void intoTasktray(HWND hwnd, const int IconID); void fromTasktray(HWND hwnd, const int IconID); void menuPopup(HWND hwnd, HMENU menu); ///////////////////////////////// ///////////////////////////////// ///////////////////////////////// /////////////////////////////////
LRESULT CALLBACK WndProc(HWND hwnd, UINT msg, WPARAM wp, LPARAM lp) { static HMENU hMenu = nullptr; switch (msg) { case WM_CREATE: hMenu = myCreateMenu();//メニュー作成 break; case WM_LBUTTONDOWN://ウィンドウをクリックしたらアイコン表示開始 { intoTasktray(hwnd, TasktrayIconID); break; } case WM_MY_NOTIFYICON: if (lp == WM_LBUTTONDOWN && wp == TasktrayIconID) { // アイコンを左クリックしたらウィンドウを表示 fromTasktray(hwnd, TasktrayIconID); } else if (lp == WM_RBUTTONUP) { // アイコンを右クリックしたらポップアップメニューを表示 menuPopup(hwnd, hMenu); } break; case WM_COMMAND: switch (wp) { case ID_MENU_MSG: // "Open"がクリックされた場合 MessageBoxA(hwnd, "MessageBox", "Info", MB_OK); break; case ID_MENU_EXIT: // "Exit"がクリックされた場合 DestroyWindow(hwnd); break; } break; case WM_DESTROY: DestroyWindow(hwnd); PostQuitMessage(0); return 0; } return DefWindowProc(hwnd, msg, wp, lp); }
int WINAPI WinMain(HINSTANCE hInstance, HINSTANCE hPrevInstance, PSTR lpCmdLine, int nCmdShow) { HWND hwnd; MSG msg; WNDCLASS winc; winc.style = CS_HREDRAW | CS_VREDRAW; winc.lpfnWndProc = WndProc; winc.cbClsExtra = winc.cbWndExtra = 0; winc.hInstance = hInstance; winc.hIcon = LoadIcon(NULL, IDI_APPLICATION); winc.hCursor = LoadCursor(NULL, IDC_ARROW); winc.hbrBackground = (HBRUSH)GetStockObject(WHITE_BRUSH); winc.lpszMenuName = NULL; winc.lpszClassName = TEXT("SZL-WINDOW"); if (!RegisterClass(&winc)) return -1; hwnd = CreateWindow( TEXT("SZL-WINDOW"), TEXT("test"), WS_OVERLAPPEDWINDOW | WS_VISIBLE, CW_USEDEFAULT, CW_USEDEFAULT, 300, 300, NULL, NULL, hInstance, NULL ); if (hwnd == NULL) return -1; while (GetMessage(&msg, NULL, 0, 0)) DispatchMessage(&msg); return msg.wParam; }
// メニューの作成 HMENU myCreateMenu() { HMENU menu = CreatePopupMenu(); AppendMenuA(menu, MF_STRING, ID_MENU_MSG, "Open"); AppendMenuA(menu, MF_STRING, ID_MENU_EXIT, "Exit"); return menu; }
// ウィンドウを消し、アイコンをタスクトレイへ格納 void intoTasktray(HWND hwnd, const int IconID) { NOTIFYICONDATA nid; nid.cbSize = sizeof(nid); nid.hWnd = hwnd; nid.uID = IconID;//複数のアイコンを表示したときの識別ID。なんでもいい。 nid.uFlags = NIF_ICON | NIF_MESSAGE | NIF_TIP; nid.uCallbackMessage = WM_MY_NOTIFYICON; //WM_USER以降の定数。 nid.hIcon = (HICON)LoadIcon(NULL, IDI_APPLICATION); wcscpy(nid.szTip, L"タスクトレイで表示する文字列"); int ret = (int)Shell_NotifyIcon(NIM_ADD, &nid); ShowWindow(hwnd, SW_HIDE); }
// タスクトレイからアイコンを削除し、ウィンドウを表示 void fromTasktray(HWND hwnd, const int IconID) { ShowWindow(hwnd, SW_SHOW); //タスクトレイアイコンを削除 NOTIFYICONDATA nid; nid.cbSize = sizeof(nid); nid.hWnd = hwnd; nid.uID = IconID; nid.uFlags = 0; Shell_NotifyIcon(NIM_DELETE, &nid); }
// ポップアップメニューを表示 void menuPopup(HWND hwnd, HMENU menu) { POINT pt; GetCursorPos(&pt); SetForegroundWindow(hwnd); TrackPopupMenu(menu, TPM_RIGHTALIGN, pt.x, pt.y, 0, hwnd, NULL); }
Rust+windows-rsでDIBを使う
CreateDIBSectionを使ってDIBを作り、CreateCompatibleDCを使って描画してみる。
各関数・データ型・定数がwindows-rsのどこにあるかさえわかれば、あとはそこまで難しくはない。
- win32dib.rs ... DIB関連の変数を一括で管理する構造体+CreateDIBSection,CreateCompatibleDCを呼び出す関数
- main.rs ... エントリポイント
- winmain.rs ... ウィンドウを表示して描画を行う
一番厄介なのはwinmain.rs内でmydibのインスタンスであるグローバル変数で、これはstatic + Lazy + Mutexで実現しないといけない。
win32dib.rs
use windows::Win32::Graphics::Gdi::*; use windows::core::*; use windows::Win32::Foundation::*; // ■ BITMAPINFO ... windows::Win32::Graphics::Gdi::BITMAPINFO // ■ BITMAPINFOHEADER ... windows::Win32::Graphics::Gdi::BITMAPINFOHEADER // ■ BI_RGB ... windows::Win32::Graphics::Gdi::BI_RGB // ■ CreatedHDC ... windows::Win32::Graphics::Gdi::CreatedHDC // ■ CreateDCA ... windows::Win32::Graphics::Gdi::CreateDCA // ■ CreateCompatibleDC ... windows::Win32::Graphics::Gdi::CreateCompatibleDC // ■ CreateDIBSection ... windows::Win32::Graphics::Gdi::CreateDIBSection // ■ DIB_RGB_COLORS ... windows::Win32::Graphics::Gdi::DIB_RGB_COLORS // ■ DeleteDC ... windows::Win32::Graphics::Gdi::DeleteDC // ■ HBITMAP ... windows::Win32::Graphics::Gdi::HBITMAP // ■ HBITMAP ... windows::Win32::Graphics::Gdi::HBITMAP // ■ SelectObject ... windows::Win32::Graphics::Gdi::SelectObject // ■ HANDLE ... windows::Win32::Foundation::HANDLE // ■ PCSTR ... windows::core::PCSTR pub struct Win32DIBCanvas{ pub bitmap :HBITMAP, pub bitmapInfo :BITMAPINFO, pub ppixel :*mut std::ffi::c_void, pub hMemDC : CreatedHDC, } // ppixel:*mut std::ffi::c_void, があるので、Send,Syncを実装しなければmyDIBをLazy<Mutex<myDIB>>に入れられない unsafe impl Send for Win32DIBCanvas {} unsafe impl Sync for Win32DIBCanvas {} impl Win32DIBCanvas{ pub fn new()->Win32DIBCanvas{ Win32DIBCanvas{ bitmap :HBITMAP(0), bitmapInfo:Default::default(), ppixel :std::ptr::null_mut(), hMemDC :CreatedHDC(0), } } pub fn create(&mut self,width:i32,height:i32){ unsafe{ let mut hdca = CreateDCA( PCSTR::from_raw("DISPLAY\0".as_ptr()), None, None, None ); self.bitmapInfo.bmiHeader.biSize = std::mem::size_of::<BITMAPINFOHEADER>() as u32; self.bitmapInfo.bmiHeader.biWidth = width; self.bitmapInfo.bmiHeader.biHeight = -height; self.bitmapInfo.bmiHeader.biPlanes = 1; self.bitmapInfo.bmiHeader.biBitCount = 3*8; self.bitmapInfo.bmiHeader.biCompression = BI_RGB; let hBitmap = CreateDIBSection( hdca, &self.bitmapInfo, DIB_RGB_COLORS, &mut self.ppixel, HANDLE(0), 0 ); self.hMemDC = CreateCompatibleDC(hdca); if let Ok(hbmp) = hBitmap{ SelectObject(self.hMemDC,hbmp); } DeleteDC(hdca); } } }
main.rs
main関数。CではWinMain開始だが、Rustではwindowsプログラムもmainから始める。
気分的にWinMainが欲しいので、main関数からWinMainを呼ぶようにしている。
mod winmain; use winmain::WinMain; use windows::Win32::Foundation::*; use windows::Win32::System::LibraryLoader::*; use windows::Win32::System::Threading::*; // ■ HINSTANCE ... windows::Win32::Foundation::HINSTANCE // ■ GetModuleHandleA ... windows::Win32::System::LibraryLoader::GetModuleHandleA // ■ STARTUPINFOW ... windows::Win32::System::Threading::STARTUPINFOW // ■ GetStartupInfoW ... windows::Win32::System::Threading::GetStartupInfoW // Rustのwindows-rsからウィンドウズアプリケーションをビルドする時には、 // WinWain ではなくmainをエントリポイントとする。 fn main()-> windows::core::Result<()> { let hInstance:HINSTANCE; unsafe{ // https://github.com/microsoft/windows-samples-rs/blob/master/create_window/src/main.rs hInstance = GetModuleHandleA(None).unwrap(); } // https://doc.rust-jp.rs/book-ja/ch12-01-accepting-command-line-arguments.html let args: Vec<String> = std::env::args().collect(); // https://stackoverflow.com/questions/68322072/how-to-get-args-from-winmain-or-wwinmain-in-rust let mut si = STARTUPINFOW { cb: std::mem::size_of::<STARTUPINFOW>() as u32, ..Default::default() }; unsafe { GetStartupInfoW(&mut si) }; let cmd_show = si.wShowWindow as i32; //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // 自作WinMainを呼び出す WinMain( hInstance, HINSTANCE(0), args, cmd_show ); Ok(()) }
winmain.rs
#[path="./win32dib.rs"] mod win32dib; use win32dib::Win32DIBCanvas; use windows::{ core::*, Win32::Foundation::*, Win32::Graphics::Gdi::*, Win32::UI::WindowsAndMessaging::*, }; use once_cell::sync::Lazy; use std::sync::Mutex; // ■ Mutex ... std::sync::Mutex // ■ Lazy ... once_cell::sync::Lazy // DIBを管理する構造体のグローバル変数 static mydib:Lazy<Mutex<Win32DIBCanvas>> = Lazy::new(|| Mutex::new( Win32DIBCanvas::new() ) ); // ■ COLORREF ... windows::Win32::Foundation::COLORREF // ■ HINSTANCE ... windows::Win32::Foundation::HINSTANCE // ■ HWND ... windows::Win32::Foundation::HWND // ■ LPARAM ... windows::Win32::Foundation::LPARAM // ■ LRESULT ... windows::Win32::Foundation::LRESULT // ■ POINT ... windows::Win32::Foundation::POINT // ■ RECT ... windows::Win32::Foundation::RECT // ■ WPARAM ... windows::Win32::Foundation::WPARAM // ■ BeginPaint ... windows::Win32::Graphics::Gdi::BeginPaint // ■ BitBlt ... windows::Win32::Graphics::Gdi::BitBlt // ■ CreatePen ... windows::Win32::Graphics::Gdi::CreatePen // ■ EndPaint ... windows::Win32::Graphics::Gdi::EndPaint // ■ LineTo ... windows::Win32::Graphics::Gdi::LineTo // ■ MoveToEx ... windows::Win32::Graphics::Gdi::MoveToEx // ■ PS_SOLID ... windows::Win32::Graphics::Gdi::PS_SOLID // ■ PAINTSTRUCT ... windows::Win32::Graphics::Gdi::PAINTSTRUCT // ■ SelectObject ... windows::Win32::Graphics::Gdi::SelectObject // ■ SRCCOPY ... windows::Win32::Graphics::Gdi::SRCCOPY // ■ CreateWindowExA ... windows::Win32::UI::WindowsAndMessaging::CreateWindowExA // ■ CS_HREDRAW ... windows::Win32::UI::WindowsAndMessaging::CS_HREDRAW // ■ CS_VREDRAW ... windows::Win32::UI::WindowsAndMessaging::CS_VREDRAW // ■ CW_USEDEFAULT ... windows::Win32::UI::WindowsAndMessaging::CW_USEDEFAULT // ■ DefWindowProcA ... windows::Win32::UI::WindowsAndMessaging::DefWindowProcA // ■ DispatchMessageA ... windows::Win32::UI::WindowsAndMessaging::DispatchMessageA // ■ GetMessageA ... windows::Win32::UI::WindowsAndMessaging::GetMessageA // ■ LoadCursorW ... windows::Win32::UI::WindowsAndMessaging::LoadCursorW // ■ IDC_ARROW ... windows::Win32::UI::WindowsAndMessaging::IDC_ARROW // ■ MSG ... windows::Win32::UI::WindowsAndMessaging::MSG // ■ PostQuitMessage ... windows::Win32::UI::WindowsAndMessaging::PostQuitMessage // ■ RegisterClassA ... windows::Win32::UI::WindowsAndMessaging::RegisterClassA // ■ WNDCLASSA ... windows::Win32::UI::WindowsAndMessaging::WNDCLASSA // ■ WS_OVERLAPPEDWINDOW ... windows::Win32::UI::WindowsAndMessaging::WS_OVERLAPPEDWINDOW // ■ WS_VISIBLE ... windows::Win32::UI::WindowsAndMessaging::WS_VISIBLE // ■ PCSTR ... windows::core::PCSTR extern "system" fn wndproc(window: HWND, message: u32, wparam: WPARAM, lparam: LPARAM) -> LRESULT { unsafe { let rectnullptr: Option<*const RECT> = None; match message as u32 { WM_CREATE => { let refmydib = &mut mydib.lock().unwrap(); refmydib.create(640,480); let hPen = CreatePen( PS_SOLID, 1, COLORREF(0x000000FF) ); // 赤いペンを作成 if hPen.is_invalid() == false{ // ペンが作成できていたら線を引く let oldPen = SelectObject( refmydib.hMemDC, hPen ); // refmydib.hMemDC の 50,50 ~ 100,100 に線を引く MoveToEx( refmydib.hMemDC, 50, 50, None as Option<*mut POINT> ); LineTo( refmydib.hMemDC, 100, 100 ); SelectObject( refmydib.hMemDC, oldPen ); // ペンを削除 DeleteObject(hPen); } LRESULT(0) } WM_PAINT => { let mut ps = PAINTSTRUCT::default(); let hdc = BeginPaint(window, &mut ps); let refmydib = &mut mydib.lock().unwrap(); BitBlt( hdc, 0, 0, 640, 480, refmydib.hMemDC, 0, 0, SRCCOPY ); EndPaint(window, &ps); LRESULT(0) } WM_DESTROY => { PostQuitMessage(0); LRESULT(0) } _ => DefWindowProcA(window, message, wparam, lparam), } } } /// 自作 WinMain pub fn WinMain( hInstance : HINSTANCE, hPrevInstance : HINSTANCE, lpCmdLine:Vec<String>, nCmdShow:i32 )->i32{ unsafe{ let _hCursor = LoadCursorW(None,IDC_ARROW).unwrap(); let _hInstance = hInstance; let _lpszClassName = PCSTR::from_raw("MY_NEW_WINDOW\0".as_ptr()); let _style = CS_HREDRAW | CS_VREDRAW; // https://microsoft.github.io/windows-docs-rs/doc/windows/Win32/UI/WindowsAndMessaging/struct.WNDCLASSA.html let wc=WNDCLASSA{ hCursor :_hCursor, hInstance: _hInstance, lpszClassName: _lpszClassName, style: _style, lpfnWndProc: Some(wndproc), ..Default::default() }; let atom = RegisterClassA(&wc); debug_assert!(atom != 0); let nullptr: Option<*const ::core::ffi::c_void> = None; CreateWindowExA( Default::default(), _lpszClassName, PCSTR::from_raw("This is a sample window\0".as_ptr()), WS_OVERLAPPEDWINDOW | WS_VISIBLE, CW_USEDEFAULT, CW_USEDEFAULT, CW_USEDEFAULT, CW_USEDEFAULT, None, None, _hInstance, nullptr, ); let mut message = MSG::default(); while GetMessageA(&mut message, HWND(0), 0, 0).into() { DispatchMessageA(&mut message); } } return 0; }
Rustでグローバル変数を作る
Rustのグローバル変数(可変)について調べた話。正直自信がない。
use once_cell::sync::Lazy; // 1.3.1 use std::sync::Mutex;
struct Foo { a: i32, b: i32, } impl Foo{ fn new() -> Foo { Foo { a: 1, b: 1, } } }
// グローバル変数 static myGlobal: Lazy<Mutex<Foo>> = Lazy::new(|| Mutex::new( Foo::new() ) );
fn call_1(){ let mut myg: std::sync::MutexGuard<'_, Foo> = myGlobal.lock().unwrap(); myg.a += 1; }
fn call_2(){ let mut myg: std::sync::MutexGuard<'_, Foo> = myGlobal.lock().unwrap(); myg.a += 1; }
fn main() { call_1(); call_2(); // myGlobal のミューテックスガードを取得 let mut myg: std::sync::MutexGuard<'_, Foo> = myGlobal.lock().unwrap(); myg.a += 1; println!("myg.a= {} , myg.b= {} ", myg.a,myg.b ); }
[package]
name = "rs-static"
version = "0.1.0"
edition = "2021"
# See more keys and their definitions at https://doc.rust-lang.org/cargo/reference/manifest.html
[dependencies]
once_cell = "1.3.1"
解説
1. staticをつける
グローバル変数はstaticをつけなければならない。
しかし、staticで定義できるのは定数のみ。従ってstaticだけではかなり限定的な使い方しかできない。
2.Mutexを使う
Mutexをつけると、
1.スレッドセーフになるのでunsafeをつけなくてもよくなる
2.内部可変性パターンにより、変数をmutableにできる
これにより、staticをつけながら可変な変数を定義できる。
つまり、可変なグローバル変数はMutexが必要。
3.Lazyを使う
Lazyは変数を遅延初期化するための機能。遅延初期化は、変数へ最初にアクセスしたときに初期化が発生するようにする。
初期化のタイミングをコントロールするためには、Lazyが必要。
正直、なくても動かすことはできる。
少なくとも、今回の小規模なプログラムに関しては。
ただ、初期化のタイミングがコンパイル時になる。さらにMutex::new()に与える引数が定数でなければならなくなるため、わざわざconst fnをimplしないといけなくなる。
4.Lazyの || とは
lazyの || は無名関数を定義するためのもので、以下のように使用する。引数、戻り値型は省略可。処理を括る{}も省略できる。
fn main() { // let func = | 引数 | -> 戻り値型{処理}; let func = | x:i32 , y:i32 | -> f32 { ( x + y ) as f32 }; let a = func(1,2); println!("a = {} ", a ); }
5.Lazyなし版
// use once_cell::sync::Lazy; //Lazyは必須ではない use std::sync::Mutex; struct Foo { a: i32, b: i32, } impl Foo{ fn new() -> Foo { Foo { a: 1, b: 1, } } const fn new_const() -> Foo {// constをつけて定数のFooを返せる Foo { a: 1, b: 1, } } } // グローバル変数 // Lazyがないときは new_constにしなければいけない static myGlobal: Mutex<Foo> = Mutex::new( Foo::new_const() ); // 以下同じ
ほかの例
Vecの例
use once_cell::sync::Lazy; use std::sync::Mutex; // グローバル変数 static myGlobal: Lazy<Mutex<Vec<i32> > >= Lazy::new(|| Mutex::new( vec![] )); fn call_1(){ let mut myg:std::sync::MutexGuard<'_, Vec<i32>> = myGlobal.lock().unwrap(); myg.push(1); }
Boxの例
use once_cell::sync::Lazy; use std::sync::Mutex;
#[derive(Debug)] struct Foo { a: i32, b: i32, } impl Foo{ fn new() -> Foo { Foo { a: 1, b: 1, } } }
// グローバル変数 static myGlobal: Lazy<Mutex<Box<Foo> > >= Lazy::new(|| Mutex::new( Box::new(Foo::new()) ));
fn call_1(){ let mut myg:std::sync::MutexGuard<'_, Box<Foo>> = myGlobal.lock().unwrap(); myg.a += 1; }
Win32API + wxWidgetsでアイコンを取得・表示
wxWidgetsでアイコンを表示したい。
HICONを wxIcon::CreateFromHICON関数でwxWidgetsのwxIconへ変換。これをさらにwxBitmapに変換する。
// https://docs.wxwidgets.org/3.0/overview_helloworld.html // プリプロセッサに以下二つを追加 // __WXMSW__ // WXUSINGDLL // サブシステムをWindowsに設定(WinMainで呼び出すので) // Windows (/SUBSYSTEM:WINDOWS) #ifndef WX_PRECOMP #include <wx/wx.h> #endif #include <wx/frame.h> // wxFrameに必要 // デバッグとリリースでライブラリを分ける #ifdef _DEBUG #pragma comment(lib,"wxbase32ud.lib") #pragma comment(lib,"wxbase32ud_net.lib") #pragma comment(lib,"wxbase32ud_xml.lib") #pragma comment(lib,"wxmsw32ud_adv.lib") #pragma comment(lib,"wxmsw32ud_aui.lib") #pragma comment(lib,"wxmsw32ud_core.lib") #pragma comment(lib,"wxmsw32ud_gl.lib") #pragma comment(lib,"wxmsw32ud_html.lib") #pragma comment(lib,"wxmsw32ud_media.lib") #pragma comment(lib,"wxmsw32ud_propgrid.lib") #pragma comment(lib,"wxmsw32ud_qa.lib") #pragma comment(lib,"wxmsw32ud_ribbon.lib") #pragma comment(lib,"wxmsw32ud_richtext.lib") #pragma comment(lib,"wxmsw32ud_stc.lib") #pragma comment(lib,"wxmsw32ud_webview.lib") #pragma comment(lib,"wxmsw32ud_xrc.lib") #else #pragma comment(lib,"wxbase32u.lib") #pragma comment(lib,"wxbase32u_net.lib") #pragma comment(lib,"wxbase32u_xml.lib") #pragma comment(lib,"wxmsw32u_adv.lib") #pragma comment(lib,"wxmsw32u_aui.lib") #pragma comment(lib,"wxmsw32u_core.lib") #pragma comment(lib,"wxmsw32u_gl.lib") #pragma comment(lib,"wxmsw32u_html.lib") #pragma comment(lib,"wxmsw32u_media.lib") #pragma comment(lib,"wxmsw32u_propgrid.lib") #pragma comment(lib,"wxmsw32u_qa.lib") #pragma comment(lib,"wxmsw32u_ribbon.lib") #pragma comment(lib,"wxmsw32u_richtext.lib") #pragma comment(lib,"wxmsw32u_stc.lib") #pragma comment(lib,"wxmsw32u_webview.lib") #pragma comment(lib,"wxmsw32u_xrc.lib") #endif #include <commctrl.h> #pragma comment(lib, "comctl32.lib") // IID_IImageList に必要 #include <commoncontrols.h>
// アイコンを取得 wxBitmap my_get_icon(const wchar_t* path) { wxBitmap ret; // システムイメージリストの取得 HIMAGELIST hImageList; HRESULT hr = SHGetImageList(SHIL_JUMBO, IID_IImageList, (void**)&hImageList); // SHIL_JUMBO 256x256 if (SUCCEEDED(hr)) { SHFILEINFO shfi; memset(&shfi, 0, sizeof(SHFILEINFO)); // path からアイコンの「イメージリスト上のインデクス」を取得 // ※ アイコンハンドルではない SHGetFileInfo(path, 0, &shfi, sizeof(SHFILEINFO), SHGFI_SYSICONINDEX); HICON hicon = ImageList_GetIcon(hImageList, shfi.iIcon, ILD_NORMAL); // wxWidgetsのwxIconに変換 wxIcon computerIcon; computerIcon.CreateFromHICON((WXHICON)hicon); ret = wxBitmap(computerIcon); // wxBitmapに変換してからDestryIconする DestroyIcon(hicon); } return ret; }
///////////////////////////////////// ///////////////////////////////////// ///////////////////////////////////// // ウィンドウ作成 class MyFrame : public wxFrame { wxBitmap mybmp_drive; wxBitmap mybmp_file; wxBitmap mybmp_doc; public: MyFrame(const wxString& title, const wxPoint& pos, const wxSize& size) : wxFrame(NULL, wxID_ANY, title, pos, size) { SetBackgroundColour(*wxWHITE); mybmp_drive = my_get_icon( L"C:\\"); mybmp_file = my_get_icon(L"C:\\Windows\\System32\\notepad.exe"); mybmp_doc = my_get_icon(L"C:\\Users\\Public\\Documents\\desktop.ini"); // PAINTイベントをバインド Bind(wxEVT_PAINT, &MyFrame::OnPaint, this); } // PAINTイベントのハンドラ void OnPaint(wxPaintEvent& event) { wxPaintDC dc(this); if (mybmp_drive.IsOk()) { dc.DrawBitmap(mybmp_drive, 5+0, 5, false); } if (mybmp_file.IsOk()) { dc.DrawBitmap(mybmp_file, 5 + 256*1, 5, false); } if (mybmp_doc.IsOk()) { dc.DrawBitmap(mybmp_doc, 5 + 256*2, 5, false); } } }; ///////////////////////////////////// ///////////////////////////////////// ///////////////////////////////////// // wxWidgetsのアプリケーション作成 class MyApp : public wxApp { public: virtual bool OnInit() { MyFrame* frame = new MyFrame("Hello World", wxPoint(50, 50), wxSize(1000, 340)); frame->Show(true); return true; } }; ///////////////////////////////////// ///////////////////////////////////// ///////////////////////////////////// // WinMainをマクロで定義 wxIMPLEMENT_APP(MyApp);
SHGetFileInfoでアイコンを取得(2) 大きなアイコン,コンピュータアイコンなど
256x256のアイコンを取得
#include<windows.h> #include<tchar.h> // HIMAGELIST // ImageList_GetIcon #include <commctrl.h> #pragma comment(lib, "comctl32.lib") // IID_IImageList に必要 #include <commoncontrols.h> #include <cstdio> #pragma warning(disable:4996) // アイコンを取得 HICON my_get_icon(const wchar_t* path) { // システムイメージリストの取得 HIMAGELIST hImageList; HRESULT hr = SHGetImageList(SHIL_JUMBO , IID_IImageList, (void**)&hImageList); // SHIL_JUMBO 256x256 // SHIL_EXTRALARGE 48x48 // SHIL_LARGE 32x32 // SHIL_SMALL 16x16 // hrからファイルのアイコンを取得 if (SUCCEEDED(hr)) { SHFILEINFO shfi; memset(&shfi, 0, sizeof(SHFILEINFO)); // path からアイコンの「イメージリスト上のインデクス」を取得 // ※ アイコンハンドルではない SHGetFileInfo(path, 0, &shfi, sizeof(SHFILEINFO), SHGFI_SYSICONINDEX); // SHGetImageListで取得したイメージリストから // SHGetFileInfoで取得したインデクスを指定してアイコンハンドルを取得 HICON hicon = ImageList_GetIcon(hImageList, shfi.iIcon, ILD_NORMAL); // ※ hiconは使わなくなったら DestroyIcon で破棄すること return hicon; } }
コンピュータアイコン
#include<windows.h> #include<tchar.h> // HIMAGELIST // ImageList_GetIcon // 表示用に ImageList_Draw も使える #include <commctrl.h> #pragma comment(lib, "comctl32.lib") // SHGetSpecialFolderLocation // SHGetFolderLocation #include <ShlObj.h> #include <cstdio> #pragma warning(disable:4996)
// アイコンを取得 HICON my_get_special_icon() { #if 0 // 注: SHGetSpecialFolderLocation は非推奨 // https://learn.microsoft.com/ja-jp/windows/win32/api/shlobj_core/nf-shlobj_core-shgetspecialfolderlocation PIDLIST_ABSOLUTE pidl; HRESULT hr = SHGetSpecialFolderLocation(NULL, CSIDL_FONTS, &pidl); #else LPITEMIDLIST pidl; // マイコンピュータのPIDLを取得 HRESULT hr = SHGetFolderLocation(NULL, CSIDL_DRIVES, NULL, 0, &pidl); // CSIDL_DRIVES マイコンピュータアイコン // CSIDL_FONTS フォントアイコン // CSIDL_DESKTOP デスクトップアイコン // ... etc #endif SHFILEINFO shfi; memset(&shfi, 0, sizeof(SHFILEINFO)); DWORD_PTR ret = SHGetFileInfoW(// イメージリストとその中のpidlで指定したアイコンのidを取得 (LPCTSTR)pidl, 0, &shfi, sizeof(SHFILEINFO), SHGFI_PIDL | SHGFI_SYSICONINDEX | SHGFI_LARGEICON); HIMAGELIST imagelist = (HIMAGELIST)ret; // アイコンリストが取得できたかどうかを表す if (imagelist != nullptr) { // imagelistからアイコンを取得 // ImageList_GetIconはアイコンのコピーを渡すので、後でDestroyIconが必要 HICON hicon = ImageList_GetIcon(imagelist, shfi.iIcon, ILD_NORMAL); // SHGFI_SYSICONINDEX を指定した場合、hIconは無効 //DestroyIcon(shfi.hIcon); return hicon;// コピーしたアイコンを返す } return NULL; }
LRESULT CALLBACK WndProc(HWND hwnd, UINT msg, WPARAM wp, LPARAM lp) { PAINTSTRUCT ps; HDC hdc; // アイコン static HICON myicon; switch (msg) { case WM_CREATE: // コピーしたアイコンを取得 myicon = my_get_special_icon(); return 0; case WM_DESTROY: // コピーしたアイコンを破棄 DestroyIcon(myicon); PostQuitMessage(0); return 0; case WM_PAINT: hdc = BeginPaint(hwnd, &ps); // アイコンを描画 DrawIconEx(hdc, 0 + 10, 10, myicon, 0, 0, 0, NULL, DI_NORMAL | DI_COMPAT); EndPaint(hwnd, &ps); return 0; } return DefWindowProc(hwnd, msg, wp, lp); } int WINAPI WinMain(HINSTANCE hInstance, HINSTANCE hPrevInstance, PSTR lpCmdLine, int nCmdShow) { HWND hwnd; WNDCLASS winc; MSG msg; winc.style = CS_HREDRAW | CS_VREDRAW; winc.lpfnWndProc = WndProc; winc.cbClsExtra = winc.cbWndExtra = 0; winc.hInstance = hInstance; winc.hIcon = LoadIcon(NULL, IDI_APPLICATION); winc.hCursor = LoadCursor(NULL, IDC_ARROW); winc.hbrBackground = (HBRUSH)GetStockObject(WHITE_BRUSH); winc.lpszMenuName = NULL; winc.lpszClassName = TEXT("SZL-WND"); if (!RegisterClass(&winc)) return 0; hwnd = CreateWindow( TEXT("SZL-WND"), TEXT("icon test"), WS_OVERLAPPEDWINDOW | WS_VISIBLE, CW_USEDEFAULT, CW_USEDEFAULT, 200, 200, NULL, NULL, hInstance, NULL ); if (hwnd == NULL) return 0; while (GetMessage(&msg, NULL, 0, 0)) DispatchMessage(&msg); return msg.wParam; }
SHGetFileInfoでアイコンを取得(1)
WindowsでSHGetFileInfoでアイコンを取得する方法。
- 引数にSHGFI_ICON を指定した場合
- アイコン(HICON)が取得できるので、そのアイコンを使用。
- 使用後はDestroyIconで破棄
- 引数にSHGFI_SYSICONINDEX を指定した場合
- 戻り値にIMAGELIST、SHFILEINFOのiIconにそのIMAGELIST内のアイコンの識別子が取得できる
- hIconは無効なので使ってはいけない
- IMAGELISTはシステムが管理しているので破棄してはいけない
SHGFI_SYSICONINDEXを指定した場合、同じアイコンはiIconが同じになるので、テーブルを作っておけばメモリを節約できる。
DrawIconEx
ちなみに下で、アイコンの描画はDrawIconを使っているが、これはアイコン本来のサイズで描画してくれないので、動作確認のためにはDrawIconExを使ったほうが良い。
DrawIconExに、第五、第六、第七引数に0を指定し、且つ DI_NORMAL | DI_COMPAT をつけて描画すると、アイコンの本来のサイズで描画できる。
DrawIconEx(hdc, 0 + 10, 10, icondrive, 0, 0, 0, NULL, DI_NORMAL | DI_COMPAT); DrawIconEx(hdc, 32 + 10, 10, iconfolder, 0, 0, 0, NULL, DI_NORMAL | DI_COMPAT); DrawIconEx(hdc, 64 + 10, 10, iconfile, 0, 0, 0, NULL, DI_NORMAL | DI_COMPAT); DrawIconEx(hdc, 96 + 10, 10, iconexe, 0, 0, 0, NULL, DI_NORMAL | DI_COMPAT);
1.アイコンを取得
本来ならCopyIconしないでそのまま返して、WM_DESTROYのところでDestroyIconすればいいが、「SHGFI_ICONで取得したアイコンはDestroyIconが必要」ということを強調するためにあえて行っている。
#include<windows.h> #include<tchar.h> #include <cstdio> #pragma warning(disable:4996)
// アイコンを取得 HICON my_get_icon(const wchar_t* path) { SHFILEINFO shfi; memset(&shfi, 0, sizeof(SHFILEINFO)); DWORD_PTR ret = SHGetFileInfoW(// アイコンを取得 path, 0, &shfi, sizeof(SHFILEINFO), SHGFI_ICON | /* SHGFI_SYSICONINDEX | */ SHGFI_LARGEICON); // retはアイコンが取得できたかどうかを表す if (SUCCEEDED(ret)) { // アイコンをコピー HICON hicon = CopyIcon(shfi.hIcon); // SHGFI_ICON を指定しているので取得したのはアイコン // なのでDestroyIconで破棄する DestroyIcon(shfi.hIcon); return hicon;// コピーしたアイコンを返す } return NULL; }
LRESULT CALLBACK WndProc(HWND hwnd, UINT msg, WPARAM wp, LPARAM lp) { PAINTSTRUCT ps; HDC hdc; // アイコン一覧 static HICON icondrive; static HICON iconfolder; static HICON iconfile; static HICON iconexe; switch (msg) { case WM_CREATE: // コピーしたアイコンを取得 icondrive = my_get_icon(L"C:\\"); iconfolder = my_get_icon(L"C:\\Windows"); iconfile = my_get_icon(L"C:\\Program Files\\Microsoft Visual Studio\\2022\\Community\\VC\\Tools\\MSVC\\14.35.32215\\atlmfc\\include\\afx.h"); iconexe = my_get_icon(L"C:\\Windows\\notepad.exe"); return 0; case WM_DESTROY: // コピーしたアイコンを破棄 DestroyIcon(icondrive); DestroyIcon(iconfolder); DestroyIcon(iconfile); DestroyIcon(iconexe); PostQuitMessage(0); return 0; case WM_PAINT: hdc = BeginPaint(hwnd, &ps); // アイコンを描画 DrawIcon(hdc, 0+10, 10, icondrive); DrawIcon(hdc, 32+10, 10, iconfolder); DrawIcon(hdc, 64+10, 10, iconfile); DrawIcon(hdc, 96+10, 10, iconexe); EndPaint(hwnd, &ps); return 0; } return DefWindowProc(hwnd, msg, wp, lp); }
int WINAPI WinMain(HINSTANCE hInstance, HINSTANCE hPrevInstance, PSTR lpCmdLine, int nCmdShow) { HWND hwnd; WNDCLASS winc; MSG msg; winc.style = CS_HREDRAW | CS_VREDRAW; winc.lpfnWndProc = WndProc; winc.cbClsExtra = winc.cbWndExtra = 0; winc.hInstance = hInstance; winc.hIcon = LoadIcon(NULL, IDI_APPLICATION); winc.hCursor = LoadCursor(NULL, IDC_ARROW); winc.hbrBackground = (HBRUSH)GetStockObject(WHITE_BRUSH); winc.lpszMenuName = NULL; winc.lpszClassName = TEXT("SZL-WND"); if (!RegisterClass(&winc)) return 0; hwnd = CreateWindow( TEXT("SZL-WND"), TEXT("icon test"), WS_OVERLAPPEDWINDOW | WS_VISIBLE, CW_USEDEFAULT, CW_USEDEFAULT, 300, 100, NULL, NULL, hInstance, NULL ); if (hwnd == NULL) return 0; while (GetMessage(&msg, NULL, 0, 0)) DispatchMessage(&msg); return msg.wParam; }
2.アイコンリストを取得してからアイコン取得
よく考えたらImageList_GetIconの時もDestroyIconが必要なので上と合わせるべきなのだが間違っているわけではないというかむしろこちらが正攻法だと思うのでこのままにしておく。
#include<windows.h> #include<tchar.h> // HIMAGELIST // ImageList_GetIcon // 表示用に ImageList_Draw も使える #include <commctrl.h> #pragma comment(lib, "comctl32.lib") #include <cstdio> #pragma warning(disable:4996) // アイコンを取得 HICON my_get_icon(const wchar_t* path) { SHFILEINFO shfi; memset(&shfi, 0, sizeof(SHFILEINFO)); DWORD_PTR ret = SHGetFileInfoW( path, 0, &shfi, sizeof(SHFILEINFO), /*SHGFI_ICON |*/ SHGFI_SYSICONINDEX | SHGFI_LARGEICON); HIMAGELIST imagelist = (HIMAGELIST)ret; // アイコンリストが取得できたかどうかを表す if (imagelist != nullptr) { // imagelistからアイコンを取得 // ImageList_GetIconはアイコンのコピーを渡すので、後でDestroyIconが必要 HICON hicon = ImageList_GetIcon(imagelist, shfi.iIcon, ILD_NORMAL); // SHGFI_SYSICONINDEX を指定した場合、hIconは無効 //DestroyIcon(shfi.hIcon); return hicon;// コピーしたアイコンを返す } return NULL; } /* 上と同じ */